- コラム
- スタッフコラム
2020.02.06
猫が食べてすぐ吐く?原因と効果的な対策を知ろう!

猫が食事を吐いてしまう…という状態は、猫と暮らしていると、比較的よく見る光景かもしれません。もちろん、猫によっては体質的に吐きやすい猫、そうでない猫と個体差はあります。
野生のころと比べると人間と一緒に暮らすようになり、猫はライフスタイルが大きく変わりました。野生のころのように、気ままにお腹が減ったら狩りをする、新鮮な獲物を食べる…といった生活から、人間のライフサイクルに合わせた時間にキャットフードなどを食べるようになりました。猫の食事スタイルや生活環境の変化も起き、次第に猫たちは「吐く」ことが増えていったのかもしれません。
今回はそんな猫たちの「吐く」について、代表的な5つの原因と対策をご紹介します。
猫が吐き戻す代表的な5つの原因と対策
猫がキャットフードを吐き戻してしまう時、考えられる理由はいくつかあります。それぞれの理由と対策をご紹介します。
※基本的に猫が吐き戻した後に元気に過ごしている場合を想定しています。吐き戻したあと、ぐったりしていたりいつもと様子が違ったりするなど、異変を感じたら速やかに動物病院で相談しましょう。
■換毛期で胃にヘアボールが出来ている
猫たちが吐き戻すものには、キャットフード以外にも異物や毛玉(ヘアボール)などがあります。特に換毛期の猫たちは、グルーミングによって体内にかなりの量の死毛(抜け毛)を取り込んでしまうため、定期的に吐き出したり、ウンチとして排出したりしています。その際に一緒に未消化のドライフードなどを吐いてしまうこともあるようです。
季節の変わり目や、特定の期間だけ吐き戻しをするなどしている場合は、消化器系の中に毛玉が溜まってしまっているのかもしれません。胃の中で大きくなりすぎた毛玉は、消化器系を塞いでしまうこともあります。ウンチが何日も出ていなかったりする場合には、速やかに動物病院などで相談してください。
■ 換毛期で胃にヘアボールが出来ている場合の対策
・こまめなブラッシング
一般的に、長毛の猫のほうが体内でヘアボールができやすい傾向にあるといわれています。そのため、長毛猫と暮らしている方はこまめなブラッシングで死毛を取り除き、猫が大量の毛を飲み込まないようにすることが予防になります。
また、健康な猫の場合は毛を飲み込んでしまっても、食事と一緒に腸へと運ばれ、ウンチと一緒に排出されることが多いです。そのため、猫がいつも通りウンチをしているかしっかりチェックすることも大切です。
《便秘傾向がある猫に》
tama たまサプリ ベンスルー
■早食いをしすぎてしまう場合

猫たちはおいしいごはんが大好きです。お気に入りの食材や、キャットフードが出てくるとついつい嬉しくて早食いになってしまうこともあるようです。また、食事と食事の時間が開きすぎてしまい、強く空腹を感じることでも早食いになりやすくなります。
急いで食べることで、ドライフードの場合、胃の中で水分を吸収しふやけると、急激に膨張し、胃が圧迫され、嘔吐してしまうというわけです。
また、諸説ありますが、早食いは食事だけではなく空気を一緒に飲み込んでしまい、胃の中の食べ物を空気が押し出す形で吐いてしまう…ということもあるようです。
このケースは、野良猫だった経験がある猫や、きょうだい猫と食事の取り合いをした経験がある猫、多頭飼いの環境で起きやすくなるようです。「自分の食事をしっかりと確保しなくてはいけない」と猫が学んでしまうことで、早食いをするようになるケースがあるようです。
また、猫たちの食事風景を観察していて、キャットフードを急いで食べているようであれば、勢いよく食べ過ぎてしまい、キャットフードを吐き戻している可能性があります。
■ 早食いをしてしまう場合による吐き戻しの対策
・食事回数を増やす
早食いをしてしまう猫たちにできる対策としては、食事の回数を増やすことがあります。一度に与える量を減らし、回数を増やしてキャットフードを食べさせるようにすることで、早食いを予防することができるかもしれません。
また、オヤツを活用して食事と食事の間の空腹感を紛らわせることも効果があります。
多頭飼いの場合は、ほかの猫にごはんを取られたり、邪魔されていなかったりを確認してみてください。もしかすると、食事を安心して食べることが出来ないために、急いで詰め込んでしまう傾向があるのかもしれません。
その場合には、ほかの猫と食事を与える部屋を別にしたり、ケージなどを活用して猫がゆっくりと満足するまで自由なペースで食べられるように工夫をすることが、効果を発揮する可能性があります。
・食事制限を行い、適切な量を与える
上記の食事の回数を過食気味の場合、猫が食べすぎてしまう・増やす対策にプラスして、適切な量に食事を制限することが有効です。
キャットフードのパッケージの裏を見てみると、1日に与えるべき目安量が記載されています。猫が食事をおねだりしてくると、ついついあげてしまいたくなるものですが、それが原因で吐き戻してしまっている場合も考えられます。
また、同じ量であっても、複数回に分けて与えることによって一度に食べる量を調整することができるため、吐き戻しの対策にもなります。
・フードの粒(キブル)を大きくする
また、キャットフードの粒を少し大きめのものに切り替えたり、お気に入りの小さめの粒のフードに粒の形や大きさが異なるフードを混ぜてみたりすることもオススメです。
大きめの粒のフードは、飲み込むまでにしっかり噛む必要があるので、食べるスピードをゆっくりにする効果があります。口いっぱいにフードを入れることもできなくなるので、空気ごと飲み込むことも少なくなるようです。
猫が食べやすい大きさの粒は、個体差がありまちまちですが、丸飲みしやすい猫のためにtamaでお取り扱いしている、大きめ粒キャットフードの特集記事も参考にしながら、選んでみるのもオススメです。
猫の狩猟本能を使って一気食い予防
*1 猫本来の習性を考慮し、ご飯はフードボールで定期的に与えるのではなく、少量を何度かに分けて探させ、自分で狩りをしているかのような体験を与えられる商品です。 NO Bowl Cat Feeder ノーボウルキャットフィーダー
■胃のサイズによる過食
猫は本来、胃が小さな動物であり、狩猟生活を送っていた時代には、1日に何度も小さな獲物を捕まえて食べていたと考えられています。そのため、猫は一度に大量の食事を摂ることができません。
しかし、現代の飼育環境では、1回の食事で必要な栄養やカロリーを摂取しようとするあまり、過剰に食べさせてしまうことがあります。過食や肥満のリスクが高まるため、食事の管理には十分な注意が求められます。
■胃のサイズによる過食による吐き戻しの対策
・高カロリーのフードを選択する
胃が小さい猫には、高カロリーのフードを与えることが効果的です。高カロリーのフードを選ぶことで、少量でも必要な栄養をしっかりと摂取でき、胃への負担を軽減することが可能です。ただし、カロリーが過剰なフードを選ぶと肥満のリスクが増すため、猫の体重の変化に気を付けながら、適切な量を与えるようにしましょう。 また、消化器サポートが施されたフードは、胃腸に優しく、消化不良や過食を防ぐことができるよう、配慮されたものも。
■キャットフードが体質に合っていない
猫も人と同様に食事に関する好き嫌いのほか、キャットフードが体質に合う・合わないがあります。食事に含まれている原材料が合わなかったり、形状や大きさが合っていなかったりすることが要因で吐き戻すことがあるのです。吐き戻しのタイミングは、食べてすぐだったり、しばらく経ってからだったりとまちまち。子猫から成猫、成猫からシニア猫になるタイミングでキャットフードを変える場合、体質に合うかも様子見しましょう。
キャットフードは猫の体調を維持・改善するためのものですが、猫に合ったキャットフードを選ぶことが重要です。
■キャットフードが体質に合っていない場合の対策
・フードを変えてみる
キャットフードが要因で吐き戻してしまう場合は、キャットフードを変えてみましょう。キャットフードを変える際には、いきなり変えてしまうとストレスに感じてしまうため、徐々に変えていきます。既存のものに新しいものを混ぜていき、徐々に新しいキャットフードの比率を上げることで、自然と変えられます。
吐き戻しがなくなった場合でも、そのキャットフードが必ずしも体質に合っているとは限りません。猫の体調や食事に対する反応は個体差があるため、継続的に様子を観察し、必要に応じて獣医師に相談することが大切です。
■食事の姿勢
猫が食事の際に取るべき姿勢は、頭が胃よりも下がっていないこと、床と並行気味になっていることが理想的だと考えられています。頭が胃よりも上がっていたり、床と並行気味でなかったりすると、食べたあとの吐き戻しにつながる場合もあります。食事が合っていて体調が良さそうにも関わらず吐き戻してしまうときは、食事の姿勢を見てみましょう。
■食事の姿勢による場合の対策
・脚付きフードボールに変える
食事の姿勢により吐き戻していると考えられる場合は、脚付きのフードボールに変えてみましょう。
子猫からシニア猫まで頭の位置は異なっているため、年齢や背の高さなどに合わせた最適な食事環境を整えることが重要です。成猫の場合、フードボールの高さは5cmから8cm程度がベストだといわれているため、調整してあげましょう。また、胃が圧迫されないことにより食欲がもとに戻る可能性もあります。
猫が吐いたときの注意点
猫はさまざまな理由により吐き戻してしまうことがあり、ご家族では理由や判断が難しいことが多いです。吐き戻しの回数が多いなど、普段と異なることがあれば、動物病院にかかるようにしましょう。より詳しく、正確に診察してもらうため、下記のように吐しゃ物の様子をこまめに伝えることが重要です。
・透明な液体や白い泡を吐いていないか?
・血が混じっていないか?
・茶色っぽい吐しゃ物ではないか?
・毛玉をはじめとした不純物は含まれていないか?
・下痢や発熱を発症していないか?
正確な診察をしてもらうために、メモに記載するだけではなく動画や写真に残しておくと良いでしょう。
おわりに
猫たちの良くみられる行動のひとつである吐き戻しですが、猫たちが吐き戻してしまう原因によって対策を行っていけば、ある程度は防ぐことが可能です。また、とある研究チームによって、製造に使用するエクストルーダーという機械に改良を加えたり、原材料の微調整、粒を成型する工程にひと工夫加えたりすることで、猫の吐き戻しを軽減することができる、という研究結果が発表されました。
今後は猫たちの吐き戻しを予防するために企業独自の工夫を凝らしたさまざまなキャットフードが登場していくことになるのかもしれません。
しかし、猫は本来吐き戻しをすることも自然な行動ですので、吐いてしまったとしても本人(猫)には悪気があるわけではありません。速やかに拭き取ったり、今回ご紹介した予防策を取り入れたりするなどして、猫たちと楽しい暮らしを送る際の参考になれば幸いです。
■tamaのメルマガ講読で最新の猫の健康コラムを読む
火曜日・木曜日・金曜日に配信するtamaのメルマガでは猫の健康の最新情報や、プレミアムキャットフードのお得な情報などをお届けしています。



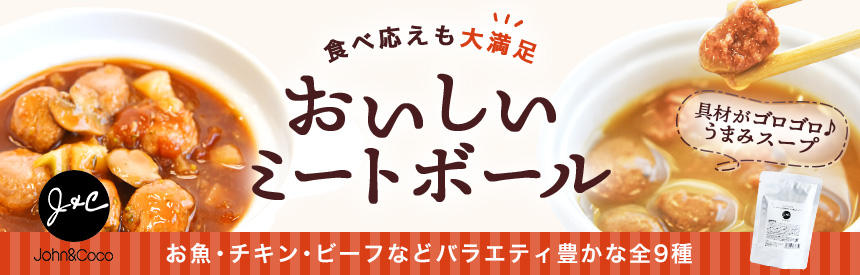



![猫が1日に16時間も寝る理由と活動時間を徹底解説[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/10087_00033_1.jpg)
![猫が尻尾を左右に振るときの気分や感情とは?尻尾でわかる心のサイン[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/10087_00027_1.jpg)
![猫にとうもろこしは大丈夫?キャットフードにも使われる理由と安全性を解説[#調査隊レポート]](../../../../ext/magazine/images/10087_00031_1.jpg)














