- コラム
- スタッフコラム
2023.05.11
猫の食事は何時に何回与えるべき?食事時間の注意点と管理のコツ
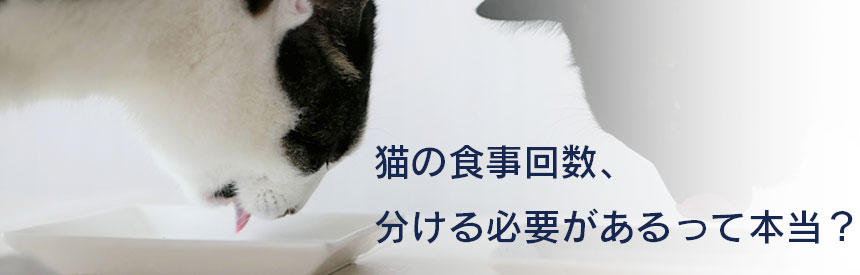
皆さまの家では、猫に1日何回食事を与えていますか?1日に3回、人間の食事の時間に合わせて与えているという方や、1日に何回も分けて与えている方、自動給餌器で管理しているという方もいるかもしれません。
キャットフードのパッケージなどでは、成分分析表や原材料と一緒に「給与量の目安」は明記されていることが多いですよね。
でも、給与量の目安はあっても「1日に何回与えてください」という食事の回数まで指定されているものは、まず見かけません。猫の食事回数は、分ける必要があるのでしょうか?
そして、猫の食事は何回に分けて与えるべきなのか、何時に与えるのが良いのかなど、正解はあるのでしょうか?
今回は、改めて猫の食事回数やタイミングについて考えてみます。
猫の食事は1日に何回与えたら良い?
では、猫の食事は1日に何回与えれば良いのでしょうか?
こちらでは、猫の食事回数についてご説明します。
食事の回数は1日に2回以上がおすすめ
猫の胃は小さく、大量の食事を一気に消化・吸収することが苦手なため、1日2回以上がおすすめです。
キャットフードを見てみると、「1日に〇回以上」「体重〇kgにつき〇gを目安に」といった表記が記載されている場合も。
食事を分ける際は、できるだけ均等に分けましょう。たとえば、1日60gの食事を与える場合、朝・晩に30gずつや、朝・昼・晩に20gずつなどが挙げられます。
年齢や健康状態に合わせて食事回数を調整しよう
年齢や健康状態はそれぞれで異なるため、それらに合わせて食事回数を調整することが重要です。
また、子猫と大人の猫でも食事量が異なるため、先述したように体重や年齢などにより適量を与えることが重要です。
前提として、猫の体調があまり良くないと思ったときは、自己判断ではなく動物病院で診療してもらいましょう。>
猫の食事回数は分けるべき?

インターネットで調べたり、「猫の育て方」的な本を読んだりしても、”猫の食事回数は数回に分けて与える”と紹介されていることが多いようです。そのため、1日で何回かに猫の食事を分けて与えるという方は多いと思います。このように、何度かに分けて猫にキャットフードを与える必要はあるのか、猫にとって適切な食事の回数というものはあるのかと疑問に思うこともあるでしょう。
猫にとってベストな食事の回数は決まっていないものの、前項でもご説明したように1日の食事回数は2回以上がおすすめであると言われています。
猫は犬と異なり、一度に大量の食べ物を食べるということができません。その際に必要な量だけを食べる生き物です。基本的には猫は自分で食べたいペースで食べるため、それが適した食事回数ということになります。大量にフードが置いてあったとしても、猫はそのフードを「ちょこちょこ食べ」して、そのときに食べたい量だけを食べていきます。この「ちょこちょこ食べ」は、猫が1日に何度も狩りを行ってその都度食事を食べていたころの名残でもあります。
家族が仕事をしていて毎日こまめに食事を与えることができない、という家庭も多いと思います。しかし、食事回数が大まか(1~2回/日)になっているせいで猫の健康を害するということはありません。
猫だって、ある程度は家族のライフスタイルに合わせることもできるため、こうしなければいけない、ということはありません。
猫がちょこちょこ食べする理由
そもそも、猫という動物は毎日決まった回数食事をする生き物ではありません。野生の環境では、毎日毎回食事にありつけるということ自体、ほとんどありません。
野生の猫は毎日狩りをして食事となる獲物をとっていたため、狩りが上手くいった日には食事を食べられますが、しかし、狩りに失敗したり獲物が見つからなかったりするときには食事にありつけない、ということが当たり前。猫はハンターであり、自分で食事を探す生き物です。また、猫は一度に大量に食べ溜めるということができないため、小さな獲物を1日に何度も狩りをして暮らしていました。
このころの名残で、猫は”一度に大量に食べるのではなく、何度かに分けて食べる”という習性を持っているのです。この1日に何度も狩りを行う習性から、常にいつでもハンティングモードに入れるようにお腹いっぱいになるまで食べなくなった…という説もあるようです。それと合わせて、自分で狩りをして獲物を捕らえ、食べるという習性のほかに、”新鮮でフレッシュなものを好む(風味が落ちると食べなくなる)”、”食事を得るための手段として狩り(遊び)がとても大切”といった習性も、野生時代の食事スタイルに由来していると考えられています。
猫の食事を数回に分けるメリット、デメリット
それでは、改めて猫の食事を数回に分けて与えることのメリット、デメリットを整理していきましょう。
食事回数を分けるメリット
・鮮度が高い食事が食べられる
・酸化のリスクを抑える、衛生的
・他頭飼いの場合、食事の量のコントロールがしやすい
食事回数を分けるデメリット
・1回あたりの食事量の調整をする必要がある
・1日あたりの量を管理できない場合、食べすぎになりやすい
・外出時間が長いと実現が難しい
猫の食事は1日に数回に分けて与えることがある意味で「常識」のようになっていますが、改めて整理してみると多頭飼育でなければそこまで大きくメリット/デメリットの差があるわけではないと思います。
猫の適切な食事回数というものは、決まっているわけではありませんし、猫によってまちまちです。それぞれの家庭によってライフスタイル、猫の食事スタイルも異なります。
色々考えてみて、やっぱり1日に何回かに分けて食事を与えたい、でも家族が仕事をしていたり、深夜は家族が寝ていたりして、留守中に何度も食事を与えることが現実的ではない…、という方も多いと思います。
そんな時は自動給餌器を活用しましょう。
決まった時間になると決められた量が自動で出てきて猫が食事をとることができます。自動給餌器で与える量を設定することもできるため、猫が無理なく食べ切れる量を与えれば衛生面でも安心です。
※基本的に、自動給餌器が使えるのはドライフードのみです。(例外的に保冷剤を入れて使うものもあるようです)
猫に食事を与えるベストなタイミングは?
猫によって食事を与えるタイミングは異なりますが、一般的には朝と夜の2回が理想的だといわれています。朝と夜の2回であれば、食事と食事の間隔が程よく空くため、猫が空腹になりすぎたり、食べすぎたりするのを防げます。
また、日中仕事をしている人が猫と暮らす場合でも、朝と夜であればご飯を出すタイミングは作れるのではないでしょうか。
猫の食事で気をつけるべきポイント
猫の食事はあげるタイミング以外にどんなことに気を付ければいいのでしょうか。
■猫のご飯が余ってしまったときは下げる
猫がご飯を残してしまうこともあるかと思います。もったいないようにも感じるかもしれませんが、そのままにしておくと菌が繁殖したり、味が変わってしまったりすることはもちろん、フードに含まれる脂質が有害な物質に変化(酸化)してしまう場合も。基本的にはお皿に残っているフードは半日を目安に一旦下げるのが良いでしょう。
なるべくは新鮮なものをいつでも用意してあげるのが理想です。
子猫や病気の治療中の猫は、何回かに食事回数を分ける。

消化器系が未発達な子猫や、病気治療中の猫の場合は家族が食事の回数をコントロールする必要があります。
子猫は空腹状態が続くと、血糖値が急激に下がり低血糖症になってしまうケースもあります。低血糖症は重篤なものでは死に至る場合もあるため注意が必要です。低血糖症を予防する目的で、子猫の食事は意識的にこまめに少量を数時間おきに与える必要があります。
また、病気の治療中の猫でも同様で、とくに糖尿病の猫では血糖値のコントロールのために食事の回数を指導されることもあります。
猫に与えてはいけないもの
猫の食事はキャットフードや猫用と記載されたものが基本ですが、人間用の食材をあげる場合、与えても良いもの、与えてはいけないものなどがあるのでしょうか。
猫に与えてはいけないものを下記にまとめます。
与えてはいけないもの
・ネギ類
・チョコレート
・ぶどう、レーズン
・そのままの状態の鶏の骨
・ユリ科など一部の観葉植物
・アレルギーとなる食品
これらを摂取してしまうと、下痢や嘔吐など、さまざまな体調不良が表れてしまう可能性があります。販売されているキャットフードに猫にとって毒となるような原材料が含まれていることは考えられませんが、好奇心旺盛な猫のこと。誤飲などで猫が口にすることがないよう、しっかり注意しましょう。
おわりに
今回は、適切な猫の食事回数やタイミング、気を付けるべきポイントについてご紹介しました。猫はもともと、少しずつ食事をする動物で、自分である程度食事の回数をコントロールしています。
少し前まで、猫たちは家の中のネズミなどを捕まえるという仕事をしていましたから、それも食事の一環だったと考えられています。
現代の猫たちは、ネズミを捕まえるという仕事をしなくなり、食事を私たち家族から与えられるようになりました。
それぞれの猫の性格や環境ごとにマッチした食事のスタイルがあると思います。
しかし、猫の胃は小さく、大量の食事を一気に消化・吸収することが苦手なため、1日2回以上がおすすめです。年齢や健康状態はそれぞれで異なるため、それらに合わせて食事回数を調整することも重要ですが、猫の体調があまり良くないと思ったときは、自己判断ではなく動物病院で診療してもらうようにしましょう。







![猫の冬の健康対策|寒さで起こる症状と予防法を徹底解説[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/neko-fuyu-kenko-yobou_main.jpg)
![猫の病気のサインを見逃さない!体調変化に気づくための観察ポイントと受診の目安[#獣医師監修]](../../../../ext/magazine/images/signs-of-illness2025_main.jpg)
![猫と人間の違い【共生編】 なぜ肉食獣の猫は人間と暮らせるのか?[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/cat-symbiosis_main.jpg)











